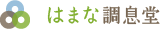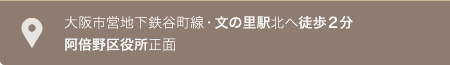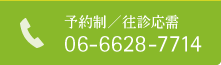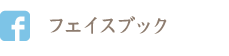2019年08月05日:
足し算と引き算の2(中毒について)
category: からだをととのえる
8月初旬は、ここ大阪は阿倍野の松崎町にあるはまな調息堂が正式に営業を始めた頃である。
2013年に開業して6年が過ぎた。
本当にあっという間の6年、ご縁を得て関わっていただいた全ての皆様に心から御礼を申し上げます。
そして7年目に入りますが、引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。
調息整体の源流にあたる野口整体の創始者である野口晴哉師は、伝統医学である鍼灸や漢方の文献もかなり読んでいたように思われる。
実際、「風邪の効用」には幕末の漢方の大家であった浅田宗伯からの引用が出てくるし、また、沢田流鍼灸術の澤田健の弟子に教えた覚え書きである「鍼灸真髄」を読むと、整体理論に出てくることがそのまま載っていたりもする。
日本の伝統医学は江戸期に大陸との交流が制限されたことによって、大陸とは違った発展を遂げた。(この成果は、明治新政府による西洋医学重視の政策転換により民間に文献が流出などしたことで、清朝末期の中医に伝えられてもいる。)
その中でも宋代以前の古典回帰を唱えた古方派の代表的漢方医である吉益東洞の唱えた
「万病は唯一毒、衆薬は皆毒物なり。毒を似て毒を攻む。毒去って体佳なり」
という「すべての病気はひとつの毒に由来しその毒を排除することが治療の根本である」とした「万病一毒説」は、その後の日本の伝統医学に大きな影響を与え、現在の漢方の基礎になったと言われている。
野口晴哉師はこの「万病一毒説」の「万病は唯一毒、毒去って体佳なり」を整体の理論に組み込んだ上で、(東洞の息子である南涯が万病一毒説を発展させ唱えた気血水論の影響もあるので、こちらが元かも知れない。)独自の発展をさせている。
それが「中毒」という状態の設定であり、その中毒を解消するための「中毒操法」(基本操法第一)である。
「中毒」とは、血液を全身に送る心臓と解毒作用を担う肝臓の血液の環流(腹心環流)が滞り、体内に毒が溜まった状態を指すのだが、調息整体や野口整体では上記の「万病一毒説」と同様、ほとんどの疾患は「中毒」状態が根底にあることで引き起こされるとしている。
そして、先ずはその中毒の解消を行うべきとしている。
昔、高齢者で健康食品を何種類もとり続けて視力が低下した方がいた。
血液検査により肝臓の機能低下が出ていたが、さらに肝臓に効果のある健康食品を増やしてそれを改善しようとされていた。
また、がんの手術の後、がんに効くと評判の治療法や健康食品を10種類近くやっていて、肩が挙がらなくなった方もいた。
デトックスを進めたが、コーヒーエネマの腸洗浄で対応しようとされた。
お二人とも操法を一定期間したものの、まったく効果が出なかった。
なんのことはない、中毒状態の解消がまったくできなかったのだ。
まず、健康食品に分類される力の強い食品は、薬そのものだ。
日本の薬事法に適わないから薬とされていないだけで、中には海外では薬として認定されているものもある。
そしてまた、
「体のある状態を"壊す"のにその毒が有効である。」
としたものを薬としただけで、吉益東堂が
「衆薬は皆毒物なり。毒を似て毒を攻む。」
と述べたように、薬は毒そのものでもある。
お二人は元々が中毒状態だったにも関わらず、さらに毒を摂取し続けて止めることをしなかった。
汚く濁ったどぶ川に栄養剤だのなんだの放り込んでも川は綺麗にならない。
誰かが川のどこかで一生懸命に川さらいをしてもジャバジャバと汚染物質が流入し続ければ、やっぱり綺麗にならない。
調息整体に伝わる中毒操法やコーヒーエネマなどは「川さらい」であり、汚染物質の流入を妨げるものではない。
お二人は、まずはどぶ川に流れ込む汚染を止める必要があったのだ。
その上での中毒操法である。
野口整体系の人たちが体の異常に対して「引き算」で考えるのは、
こういった中毒の背景もあるのだ。