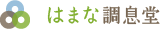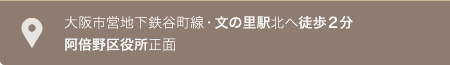2018年05月10日:
百尺の竿頭の上にたって見えたものは??
category: よもやま話
GWも終わり平成も残すところ1年と迫ったものの、ここ大阪は阿倍野区松崎町は寒暖の差が激しい日が続き調息整体や親流儀である野口整体の観方だともう梅雨の体になりだしているのだけど、日中でも肌寒い時間があり、当堂も暖房器具が終えないでいる。
百尺の竿頭の上に立って、さらに一歩を進めよ。
臨斉禅の古典である「無門関」に出てくる禅語である。
高校時分に宮本武蔵の「五輪書」を読んだ際、巻末の鎌田茂雄さんの解説で出会った。
「百尺(約30m)の竿の頭まで苦労して上り詰めた=修行を積み悟りを得た境地にあってそこに安住せず、さらに一歩を進めなさい。」
という意味である。
しかし、この言葉、想像してみるととても怖い状況だということに気づく。
先ず
「30mの立てられた竿の上に立つ」
どれだけの直径なのか分からないがこんな高い竿の先端は当然、揺れて不安定なわけで危険極まりない。その危険な先端に立った上でさらに、
「一歩を進めよ」
と言われているのである。
それは30mの上から墜ちろ、つまり、「死ね」と言われているに等しい。
ぼくはこの禅語が白血病の闘病中いつも頭の片隅にあった。
実は当時のぼくはこの禅語の意味を
「死の瀬戸際に立たされている状況で、さらに一歩を進めなさい」
と少し間違えて解釈していたのだけど、それが白血病という死と生の狭間に置かれた闘病生活をしている自分の状況にとても良く似ている気がして、そこから一歩を進める=死を意識したときに果たして自分は何が見えるのだろう??と臨斉禅における公案のようにずっと考え続けていたのだ。
26歳という世界に自分の居場所を構築しなければならない大切な時期にあって、長期に及ぶ闘病生活は病との戦いだけでなく、生死と生き延びた後に続くその後の人生に対しての不安と絶望と孤独とも戦わなければならなかった。
前骨髄球性型急性白血病という白血病の中でも96年に分化型療法という治療法が確立されたことで他の白血病と比べて体に負担の少ない治療になり完治率も段違いに高くなったとはいえ、大量の抗がん剤を使う過酷な治療であることに変わりはなく、
明日に生きている保証はどこにもない現実と、10年後、20年後の自分の為にそれまで数年にわたり必死に取り組んでいたものが全て真っ白になり、一からやり直しどころかやり直せるのか??という未来がぼくの上に分厚くのしかかってきて、周囲に何もない暗い深海の底にたった一人でいるような感覚に陥り、どうしようもない不安と絶望と孤独が襲ってきたのだ。
そんな日常においてこの言葉は、遥か高くにある海面から差し込んでくる小さな光のような存在となり、不安と絶望の中から活路を見出すための大きな支えになった。
言葉にできない何かの感覚をつかんだ気は闘病生活すぐにあった。
しかしそれが何かは分からなかった。
それが分かったのは化学療法の第一クールが終わり、数日間の帰宅許可が出たときである。
一ヶ月間、ほとんどベットから動くことが出来ず、全身が衰え数メートル歩くだけで疲労するような状態で母に付き添われながら帰宅すると、玄関の前で飼っている愛犬が尻尾を目茶苦茶に振って出迎えてくれた。
出迎えてくれるのは毎度のことなのだが、いつもなら前を歩いている母に先ず飛びつき頭を撫でてもらってからぼくに飛びつくのが、その日は母を「邪魔!!」とばかりに鼻で押しのけぼくに飛びついてきたのだ。
と同時に、大雨の晩に一匹だけ側溝に落ちてふるえていた目も開いてないのをぼくが拾ってきた愛猫が門柱に駆け寄ってきてニャーと一鳴きした。
彼らの行動を見た時、ぼくは彼らがぼくの長い不在をとても心配してくれていたのを理解した。
その瞬間ぼくは、
「ぼくという存在は何かの存在に生かされ、またぼくという存在は何かの存在を生かしている。」
という、全ての存在はどんな時もどんな場所にいても繋がっていて、支えあっていることを理屈抜きで実感したのだ。
この実感が正しいのか間違っているのか分からないし確かめる術もない。
ただ、ぼくはこれ以降、生きていることの素晴らしさを実感し、次に起る出来事が例え死に直結することでも客観的に観察し楽しむことができるようになり、不安も絶望も孤独もどんどん薄れていった。
百尺の竿頭の上に立ち一歩を進めてみたら、ぼくには全てと繋がった光輝く世界が待っていたのである。